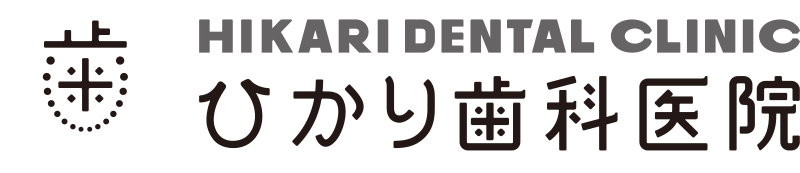乳歯の歯並びが悪い…すぐに矯正治療は必要?
【監修:歯科医師 長谷川雄士】

お子さんに乳歯が生えている時期に歯並びが悪くなっていると、心配される親御さんも多いです。実際、乳歯の時期の歯並びについては、経過を見る場合と早い段階で矯正治療が必要になる場合があります。
今回は乳歯の歯並びについて「早めに治療した方が良い場合とそうでない場合」、「治療開始時期や方法」などについてご説明します。
【目次】
1.乳歯と乳歯の間にある「すき間」について
2.乳歯において早期に矯正治療が必要なケースと不要なケース
2-1早期の矯正治療が不要なケースは経過観察が大切
2-2早期に矯正治療が必要なケース
3.矯正治療の開始時期とその方法について
4.乳歯の段階で歯並びが悪い場合に引き起こされる影響
5.乳歯の段階で歯並びが悪くなる原因とは?
6.歯並びの悪化を防ぐためにできること
6-1 ①お口周りの癖や習慣を改善する
6-2 ➁予防矯正という治療方法もあります!
7.お子さんの歯並びに悩まれてませんか?ぜひ当院へご相談を!
乳歯と乳歯の間にある「すき間」について
乳歯は通常であれば上下合わせて20本存在します。その乳歯が生えそろうまでの状態を「乳歯列」と言い、最初の乳歯が生え始めてから、最初の永久歯が生え始めるまでの期間を「乳歯列期」と呼びます。
乳歯列には、歯と歯の間に隙間が見られることが多く、親御さんが心配されることもあります。しかし、実は乳歯列の歯と歯の間に隙間があることは理想的な状態なのです。
永久歯のサイズは乳歯より大きいです。そのため、乳歯列でみられる歯と歯の隙間は乳歯から永久歯に生え換わる際に、永久歯が生えるスペースを確保する重要な役割を果たします。
歯と歯の間に隙間のない乳歯列が、すべて歯並びが悪くなるとは限りませんが、永久歯の生え換わりの時期には十分な経過観察を行う必要があります。
乳歯において早期に矯正治療が必要なケースと不要なケース
乳歯の歯並びの状態によっては、早めに対応が必要な場合と、経過観察をしながら治療時期を決める場合があります。
「骨格自体に原因」があると、早めに治療をした方が良い場合があります。以下に詳しくご説明いたします。
早期の矯正治療が不要なケースは経過観察が大切
〇乳歯の前歯が傾いて生えている
乳歯の前歯が傾いて生えるケースは珍しくありません。顎が成長するにつれて徐々に改善されることがほとんどです。歯科医院で定期検診を受けながら経過観察してもらうのがおすすめです。
〇乳歯の前歯が捻れて生えている
特に一番前にある2本の前歯(乳中切歯)は捻れて生えるケースが多く、角度によって八の字に見えます。原因としては、顎の発達の遅れが生じていることが多いです。この状態も顎の成長に伴って徐々に改善されることがほとんどです。歯科医院で定期検診を受けながら経過観察してもらいましょう。
早期に矯正治療が必要なケース
歯並びや咬み合わせが悪い状態を「不正咬合」といいます。「不正咬合」にもいくつか種類がありますが、中でも早い段階で矯正治療を検討していただきたい歯並びは、「反対咬合(受け口、下顎前突)」、「交叉咬合(こうさこうごう)」、「叢生(そうせい)」、「上顎前突(出っ歯)」、「開咬(かいこう)」などが挙げられます。
不正咬合を引き起こす原因は主に「骨格的な問題」と「歯の生え方による問題」が考えられます。特に「骨格的な問題」が原因となる場合は、早めに矯正治療をご検討いただく場合があります。
4歳~5歳くらいに矯正相談をおすすめする歯並び
〇反対咬合
下前歯が上前歯より前に出ている状態の歯並びです。顎骨の位置が上下反対になっている可能性が高いため、将来的に骨格が間違った状態で成長しやすくなり、咬み合わせの異常や顎関節症を発症しやすくなります。顎の成長が進むと治療の難易度が高くなるため、早めに矯正相談を受けていただくことをおすすめしています。
〇交叉咬合(こうさこうごう)
本来、上の歯は下の歯より外側、下の歯は上の歯より内側に位置しています。しかし、部分的に上の歯が内側よりに生えていたり、下の歯が外側よりに生えていることがあります。このような状態だと、上下の歯がうまく咬み合わず、咬み合わせが悪い状態になります。交叉咬合も骨格の位置に原因がある可能性が考えられるので、顎の成長が進むと治療の難易度が高くなる場合があります。そのため、早めに矯正相談を受けていただくことをおすすめしています。
6歳くらいに矯正相談をおすすめする歯並び
〇叢生(そうせい)
歯と歯が重なって、歯並びがデコボコしている状態をいいます。顎のサイズに対して歯のサイズが大きかったり、歯のサイズに対して顎のサイズが小さい場合に起こりやすいです。歯磨きがしづらく、磨き残しができやすいため、虫歯や歯周病のリスクが高まります。
〇上顎前突(じょうがくぜんとつ)
上の前歯が前方向に突き出している状態のことをいいます。遺伝、舌で上前歯を押す癖、指しゃぶり、爪かみ、口呼吸などが原因で引き起こされやすいです。
通常より唇が閉じにくいことで、さらに口呼吸になり口の中が乾燥する傾向があります。口の中が乾燥すると、唾液の循環が悪くなり、口臭や口の中のネバツキなどが起こりやすく、虫歯や歯周病のリスクも高まります。
また、転倒した時に、衝撃によるダメージも受けやすいです。
〇開咬(かいこう)
奥歯を咬み合わせた時に、前歯が咬み合わない状態をいいます。
遺伝や、舌を前に出す癖、指しゃぶり、口呼吸などが原因とされています。
上下の前歯の間に隙間ができているため、そこから空気が漏れ、うまく発音できなかったり前歯でかみ切れなかったりするなど、日常生活に支障をきたすことがあります。また、奥歯しか咬み合っていないことで、奥歯への負担が大きく、欠けたりヒビが入ったりすることがあります。顎関節症のリスクも高まります。
いずれにしても、少しだけ前歯が出ている、少しだけ歯が重なっているなど、比較的軽度の場合は経過観察となるケースもあります。お口の状態は、実際に歯科医師に診てもらわないとわからないこともあるため、お子さんの歯並びが気になるようなら一度歯科医院を受診してみましょう。
矯正治療の開始時期とその方法について
お子さんの歯並びに気になることがあれば、矯正治療を考える方も多いと思います。子供の時期の矯正治療は、始めるタイミングによって治療の目的や方法が異なります。早めに始めるほうが治療の選択肢も多いですが、それがお子さんに必要かどうかは医師の診断を受けないとわかりません。
子供の時期に行う矯正治療には、乳歯列期から行う「予防矯正」、歯が生え換わり始めるタイミングで行う「第一期治療」、永久歯が生え揃ってから行う「第二期治療」があります。
■予防矯正■
予防矯正は、乳歯が生え揃った早い段階から矯正治療を始められるのが特徴です。早くて3歳くらいから始められることもあります。
歯が生える位置は、顎骨の発育や口周りの筋肉の発達によって決まるため、これらの発育をうまく促すことができれば歯並びも整いやすくなります。そのため、予防矯正では「上顎の発達や口周りの筋肉の発達をコントロールし、それらのバランスを改善すること」を目的とします。
早い段階で行える矯正治療であるため、歯並びの問題も比較的軽度の状態から治療を始めることができます。そのため、矯正装置も柔らかいマウスピース型の装置を使用します。日中1時間と就寝時に装着します。
それに加えて、お口のトレーニングを1日10分〜15分くらい行います。小さいお子さんでも進めやすいトレーニング内容で、装置も使いやすくなっているので、矯正治療方法の中でもお子さんの負担は比較的少ないといえます。
特に骨格的な原因のある受け口の状態が確認できる場合は、早い段階での矯正治療が効果がでやすいです。
■第一期矯正治療■
第一期治療は、6歳から12歳くらいまでの乳歯から永久歯に生え換わる時期に矯正治療を行う方法です。矯正治療の開始時期は、乳歯が生え揃った後、さらに奥に生える第一大臼歯(6歳臼歯)が生えて、前歯が生え換わるタイミングで始めることが多いです。遅くても7~8歳頃に始められれば理想的な歯並びに近づきやすいです。
第一期治療の目的は、「顎骨の発育のコントロール」「正しい呼吸法への改善」「口周りの癖の改善」「歯が並ぶアーチを拡大する」ことです。
永久歯が正常な位置に生えやすいように、顎骨の発育を促したり歯が並ぶアーチを拡げるために「拡大装置」とよばれる矯正装置を使用します。この装置は、定期的にネジを回しながら歯の裏側から力をかけ、歯が並ぶアーチを拡げて、永久歯が生えるスペースを作ります。取り外しができるので、食事や歯磨き、写真撮影など気になる時は外すことも可能です。

装置にはいくつか種類があり、「マウスピース型矯正装置」、短期間で顎を拡げられる「急速拡大装置」、取り外しができない「固定式急速拡大装置」などがあります。これらは、お子さんのお口の状態を見ながら、担当の歯科医師が使用する装置を決めます。
その他にも、上顎あるいは下顎が成長しすぎてしまい、上下の顎の大きさのバランスが悪くなっていることもあります。その場合には、顎の成長を抑制する装置を装着して顎の発育をコントロールすることもできます。また、口呼吸や舌で前歯を押す癖などが習慣化している場合は、早いうちに改善できるようにトレーニングを一緒に行う場合もあります。
■第二期矯正治療■
第一期治療だけでは改善できなかった歯並びがある場合は、引き続き第二期治療を行うことがあります。また、第一期治療の時期が過ぎてしまった場合に第二期治療を始められる方もいらっしゃいます。永久歯が生え揃い、顎骨の成長が完了している場合は成人矯正が適用されますが、成人矯正と第二期矯正治療はほとんど同じ治療方法です。
第二期治療は、親知らず以外の永久歯が全て生え揃った時期である12歳以降くらいに行います。第二期治療の目的は「永久歯の歯並びを綺麗にし、かみ合わせを整えること」です。
治療法は主に2つ、「ワイヤー矯正」と「マウスピース矯正」があります。
「ワイヤー矯正」は「表側矯正」と「裏側矯正」に分けられます。歯面にブラケットと呼ばれる装置を接着し、そこにワイヤーを通して歯を3次元的に動かします。
「表側矯正」と「裏側矯正」の違いは、装置を歯の表面に接着するか裏面に接着するかによります。そのため、「表側矯正」は装置が目立ちやすく、「裏側矯正」は装置が目立ちにくいです。装置が目立ちやすい「表側矯正」でもブラケットやワイヤーを透明や白色にすることで目立ちにくくできる場合もあります。
ワイヤー矯正は従来から使用されている方法で、歯を大きく動かすことができるので適応症例範囲が広いのが大きな特徴です。
「マウスピース矯正」は、透明の樹脂素材でできたマウスピース型矯正装置を使用します。装置が目立ちにくく、取り外しが可能なため、食事や歯磨きの際は通常通り行うことができます。
マウスピースを2週間ごとくらいに交換しながら歯を少しずつ動かしますが、自宅での交換が可能なため、通院頻度は2~3ヶ月に1回くらいと比較的少ないです(お口の状態によって異なる場合もあります)。
また、マウスピース矯正装置は1日22時間以上装着する必要があります。装着時間やマウスピース型矯正装置交換のタイミングなど自己管理が非常に重要です。
乳歯の段階で歯並びが悪い場合に引き起こされる影響
乳歯の段階で歯並びが悪い場合は、その後に生えてくる永久歯や発音機能、咀嚼機能にも影響を及ぼすことがあります。以下に、項目に分けて詳しくご説明します。
〇虫歯や歯肉炎になりやすい
乳歯の歯並びが悪いことで、歯と歯が重なっていたり傾いていたりすると、歯と歯の間や歯と歯茎の間に汚れが溜まりやすくなります。歯磨き自体も難しくなることで、虫歯や、歯茎が腫れる歯肉炎になりやすいです。歯磨きのやり方を改善できないまま永久歯に生え換わると、永久歯にも同様の悪影響が及びます。
また、もし乳歯が虫歯になって大きく進行してしまった場合、乳歯の根元に存在する、これから生えようと準備をしている永久歯に虫歯菌が感染し生えてくることもあります(ターナーの歯)。
〇発音や滑舌、咀嚼機能にも影響する
奥歯を咬み合わせても上下の前歯が咬み合わず隙間ができてしまう「開咬」は、前歯で噛むことが難しく咀嚼が不十分になりやすいです。咀嚼が不十分だと、消化不良を起こしたり栄養の吸収が不十分になったりすることがあります。
また、言葉を発する際にも、隙間から空気が漏れてしまうことで発音がうまくできなかったり、滑舌が悪くなったりしやすいです。
〇永久歯が正常な位置に生えにくい
乳歯が生え揃っている状態で歯と歯が重なっていたり、歯が傾いた状態になっている場合があります。このような状態だと、永久歯のサイズは乳歯の1.5~2倍ほどの大きさがあるため、永久歯が生えるスペースが確保されにくくなります。そのため、永久歯が正常な位置に生えにくくなることで、永久歯も歯と歯が重なったり、歯が重なった状態になり歯並びが悪くなる可能性があります。
また、乳歯の歯並びが悪いことで磨き残しができ虫歯になった場合、虫歯の進行具合によっては生え換わりの時期より早く抜けてしまうことがあります。そうすると、乳歯があった部分に隙間ができてしまうため、隣の歯がその隙間に傾き、永久歯の生えるスペースがなくなり、永久歯が正常な位置に生えてこられなくなることがあります。
乳歯の段階で歯並びが悪くなる原因とは?
乳歯の歯並びが悪い原因には、生まれつき備わった「先天的な原因」と、生まれた後に何らかの要因により備わった「後天的原因」があります。
〇先天的な原因
先天的な原因として挙げられるのは、顎や歯のサイズの遺伝、歯の本数が何らかの要因で多いあるいは少ない状態であることです。
遺伝については、両親あるいは両親のどちらかが歯並びが悪いと子供も歯並びが悪くなることがあります。遺伝によって顎骨と歯のサイズのバランスが悪い場合、例えば、歯に対して顎骨が小さかったり、顎骨に対して歯が大きかったりすると、歯が生えるスペースが確保されにくくなるためデコボコした歯並びになりやすいです。また、下の顎骨が上顎より大きいと受け口になりやすいです。
他にも、歯の本数の違いによって歯並びは悪くなりやすいです。もともと数本の歯がない状態を「先天欠如歯」、歯が通常より多くある状態を「過剰歯」と言います。これらの状態により左右で歯の本数が異なると、歯並びが悪くなることがあります。
また、「過剰歯」が永久歯の萌出の妨げとなり、永久歯が生えてこなかったり傾いて生えてきたりすることも歯並びが悪くなる原因のひとつです。
〇後天的な原因
後天的な原因として挙げられるのは、生活習慣やお口周りの癖などです。
日々の生活で軟らかい物だけを好んで食べていると、飲み込みや咀嚼回数の減少に繋がり、お口周りの筋肉は鍛えられにくくなります。歯並びは、歯の内側からかかる舌の力と歯の外側からかかる頬や唇の力のバランスによって歯が生える位置が決まります。そのため、どちらかの筋力が弱まってしまうと、バランスが崩れて歯並びに影響が出てしまうのです。
また、お子さんが小さい頃には指しゃぶり、口呼吸、舌で前歯を押す癖などが見られることが多いですが、それらの癖も歯並びに関係します。
口呼吸だと、口が開いたままになることが多くて舌が下がった状態が続き、受け口や開咬などの原因となることがあります。
指しゃぶりは、4歳以降も続いてしまうと歯並びに悪影響を及ぼします。上下の前歯の間に指が挟まっていることで開咬の原因となったり、その指で上の前歯を押すことで上顎前突(出っ歯)の原因になったりすることがあります。舌は本来、上の前歯の裏側つけ根あたりにあるスポットに置くのが正しい位置です。しかし、その舌で前歯を押す癖があると、受け口や出っ歯の原因になることがあります。
この他にも、悪い姿勢やうつぶせ寝、頬杖をつく癖なども歯並びを悪くする原因として挙げられます。これらの癖は、なるべく早めに改善することが望ましいです。
歯並びの悪化を防ぐためにできること
普段何気なくしていることでも、歯に小さな力が継続的にかかると歯は少しずつ動きます。そのため、お口周りの癖があると、不必要に歯へ力がかかり歯並びも悪くなりやすいです。
歯並びの悪化を防ぐためには、早い段階でお口周りの癖を直すことが効果的です。また、乳歯の時点で歯並びに気になることがあれば、予防矯正を受けるという選択肢もあります。以下に、「お口周りの癖や習慣」や「予防矯正」について具体的にお伝えします。
①お口周りの癖や習慣を改善する
乳歯の歯並びには遺伝以外に、お口周りの癖が原因となることもあります。お子さんにお口周りの癖がついている場合は、なるべく早めの改善が必要です。永久歯の生え換わり時期まで続いていると、永久歯の歯並びを悪くしてしまう原因にもなります。
また、矯正治療により歯並びを治した後も、お口周りの癖が改善していなければ、歯並びが元に戻る「後戻り」を起こしてしまう可能性もあります。お口周りのや習慣を改善することは、悪い歯並びの根本的な改善にも繋がります。以下に、注意すべき「お口周りの癖」についてご説明します。
口で呼吸する癖
歯並びには、舌の位置や動きが重要です。
舌は本来、舌の先端が前歯の裏側のスポットと呼ばれる位置に触れていて、舌全体が上顎に吸着している状態が正常です。舌が上顎についていることで、上の歯列が裏側から押され、歯が並ぶアーチが拡がり、顎の成長が進みやすくなります。
しかし、口呼吸が習慣化していると口が開いたままになり舌が下がりやすく、顎の成長がうまく進まないことで、歯並びが悪くなる原因に繋がることがあります。
また、鼻呼吸は鼻腔というフィルタ-を通すため、外気に含まれる細菌やウィルス、目に見えない浮遊物を軽減して空気を体に取り入れることができます。しかし、口呼吸はフィルター機能がないため、直接空気を取り込んでしまうことでウィルスや細菌による感染症にかかりやすくなります。他にも口が乾燥しやすいことで唾液の循環が低下し、虫歯や歯周病リスクが高まりやすいです。
指を口にくわえる癖
小さいお子さんによく見られる癖として、指をくわえる、指しゃぶりなどがあります。この癖は、お子さんに言葉が伝わるようになる2~3歳くらいの時期から声かけをして、4歳くらいまでに改善できるのが理想的です。5~6歳くらいになると歯の生え換わりが始まるため、それまでに改善できるように促してあげましょう。
指しゃぶりは、指を吸う力がかかることで、頬の力で歯列が押され、歯が並ぶアーチが狭まりやすくなり顎の成長の妨げとなりやすいです。
また、指をくわえていることで、上下の前歯の間に隙間ができて噛み合わない状態になることもあります。なかなか癖が改善しない場合は、小児歯科や発達検査を行っている保健センターで相談してみると良いでしょう。
悪い姿勢
姿勢も歯並びと密接に関係しています。姿勢の悪さは歯並びを悪くする原因のひとつであり、歯並びの悪さも姿勢が悪くなる原因となります。小さなズレを補正するために、体がそのズレに合わせて傾くからです。
姿勢の状態により体の重心の位置が変わると、歯が咬み合う位置も変わります。猫背の状態で座ると、後方に重心がかかりやすくなり、歯を数回カチカチとかみ合わせると、奥歯を中心として歯が咬み合わさる感覚になりやすいです。両足の裏全体を床につけて前傾姿勢の状態で座ると、重心が前方にかかりやすくなり、歯を数回カチカチと咬み合わせると前歯を中心として歯が咬み合わさる感覚になりやすいです。前者の場合、食事の際にも前方に力がかかりにくく奥歯だけで咀嚼を行うことになるため、前歯や唇に力がかかりにくくなり、叢生や出っ歯になりやすくなります。
特に本を読む時、ゲームや勉強をしている時など、何かに集中している時は、無意識のうちに姿勢が悪くなり猫背になりやすいです。なるべく意識して正しい姿勢を保てるようにしましょう。
舌の癖
舌の正常な位置は、前歯の裏側のつけ根付近にある「スポット」と呼ばれる位置に舌の先端が触れ、舌全体が上顎に吸着している状態です。
舌が上前歯を押す癖があると「出っ歯」に、舌の位置が上下前歯の間に置かれる癖があると「開咬」に、舌が下前歯を押す癖があると「受け口」になりやすいです。「出っ歯」や「開咬」、「受け口」になると、上下の前歯の間に隙間があき、そこから空気がもれることでうまく発音しにくくなることがあります。
舌の裏に繋がっている「舌小帯」が短いことが舌の位置に影響している場合は、歯科医院にて「舌小帯」の処置が必要です。
舌の癖を改善するためには、舌の筋力を鍛えることも効果があるため、歯科医院で専門的な「舌トレーニング」を行うこともあります。
爪噛みや唇を噛む癖
爪噛みや唇を噛む癖があると、大きな力が歯に加わりやすいため歯並びにも影響します。
爪噛みをしていると、上の前歯が前方に傾いたり、捻れることがあります。上の前歯の歯並びが悪くなると、それらと噛み合う下の前歯も乱れてきます。また、前歯が欠ける原因になることもあります。
唇を噛むくせについては、上前歯で下唇をかむ癖があると「出っ歯」になりやすく、下前歯で上唇を噛む癖があると「受け口」になりやすいです。
これらの癖については、精神的なストレスなどを感じている場合もあるので、お子さんの話にゆっくり耳を傾けてあげるようにしましょう。他にも、十分な睡眠をとる、栄養のバランスのとれた規則正しい食事など生活面での配慮も心がけるようにしましょう。
➁予防矯正という治療方法もあります!
〇予防矯正について
永久歯が生え揃う前の時期は、体の成長期にもあたり、顎や顔の骨格も発達段階にあります。この時期の骨の状態は比較的柔らかいため、専用の矯正装置を使用して顎の成長をコントロールしやすく、矯正治療がスムーズに進みやすいです。また、顎の大きさ自体をコントロールすることができるため、歯を動かすスペースを確保するための便宜抜歯を行う確率も低いです。
お口周りの癖を改善するために、舌や唇を鍛えるトレーニングも一緒に行います。呼吸法や舌の位置、嚥下、姿勢の改善など、悪い歯並びの根本的な原因を改善することで正しい歯並びに導くことができます。
〇治療方法
精密検査で、レントゲン写真撮影、CT撮影、嚥下の状態、姿勢の状態、ぽかん口になっていないかなどを検査して記録します。その後は、1ヶ月に1回通院していただき、担当のスタッフとトレーニングの練習を行います。おうちでも毎日トレーニングを行っていただくことで、舌の正しい動かし方を身につけながらお口周りの筋肉を鍛えます。
トレーニングは、1日10分~15分程度で行なえる内容です。呼吸を改善するトレーニングや舌をお口の中で大きく動かすトレーニングなど、お子さんが楽しみやすい内容でもあります。
それと一緒に、シリコン製の軟らかいマウスピースを日中1時間と就寝時に装着していただきます。軟らかい素材のため、痛みはなくお子さんでも使っていただきやすい装置です。
お子さんのお口の状態を見ながら、顎を拡げるための装置を使用することもありますが、取り外し可能な装置のため少しずつ慣れてもらいながら使用していただくこともできます。
お子さんの歯並びに悩まれてませんか?ぜひ当院へご相談を!
矯正治療は大人になってからでも可能です。しかし、矯正治療が必要と診断された場合、子供の時期に矯正治療を始めるほうがメリットが多いです。その主なメリットとは、
- 成長期の段階で矯正治療を始めることで、歯が生える土台である顎骨へアプローチできるため、歯を動かすために必要となるスペースを確保するための抜歯をしないケースが多い。
- 早い段階で悪い歯並びの原因となりやすい、お口周りの癖や口呼吸、悪い姿勢などを改善しやすい。
- 悪い歯並びの根本的な問題を改善することで、治療後に後戻りしにくい。
- 成長期の骨は比較的軟らかく歯が動きやすいため、治療もスムーズにすすみやすく治療期間も大人の矯正治療より早めに完了しやすい。
などが挙げられます。
当院では、お子さんの健やかな成長を促すために子供の予防矯正にも力を入れております。
お子さんの歯並びはもちろん、乳歯の段階での歯並びやお口周りの癖など気になることがあればぜひ当院へご相談ください。
特に、矯正治療が必要な場合、どのタイミングでスタートすればいいか迷われる親御さんが多いです。お子さんによって歯が生える時期は異なるため、お子さんの歯の状態をもとにお話しさせていただきます。