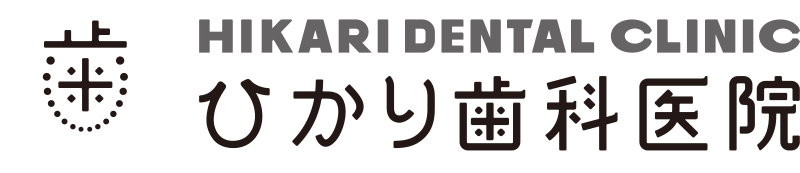受け口における症状の違いとは?症状別治療法について解説!
【監修:歯科医師 長谷川雄士】

歯並びは整っているのに、顎が前に出ているように感じる…
鏡に映った自分を見て、そのように感じたことはありませんか?
もしかすると、それは「受け口」が原因かもしれません。歯科の専門用語では、「下顎前突(かがくぜんとつ)」「反対咬合(はんたいこうごう)」と言います。
「受け口」は治療により改善することが可能です。治療を始める時期や、軽度から重度など症状の違いによって治療方法が異なります。もしかすると、長年悩んできた「受け口」が治療により数年で治るかもしれません。
このコラムでは、「受け口の原因」「症状別の治療方法」「受け口を解消しやすくなるトレーニング」などについて解説します。
【目次】
1.「受け口」ってどんな状態?
2.受け口の2つのケース「歯の生え方」と「骨格」について
2-1似ているようで違う!?「受け口」と「しゃくれ」
3.受け口を引き起こす要因「先天的要因」と「後天的要因」
4.「受け口」の症状に合った治療法とは?症状別に解説!
4-1受け口治療で外科手術が必要になるケースとは?
5.受け口は自分で改善できる?
5-1受け口を解消しやすくなる3つのトレーニング
6.当院は受け口治療も行っております!お気軽にご相談を!
「受け口」ってどんな状態?
正常な咬み合わせは、わかりやすく説明すると「上の前歯が下の前歯に被さっていて、その重なりが2〜3mmくらいになっている状態」です。
しかしながら、受け口は「下の前歯が上の前歯より前に出ている状態」になっています。この状態だと、舌の位置が下がりやすく、口も閉じにくいことで口呼吸にもなりやすく、口の乾燥により虫歯や歯周病リスクを高めてしまうことがあります。
また、発音がうまくできないこともあります(特にサ行やタ行)。
歯並びや咬み合わせが悪い状態を「不正咬合」と呼びますが、「受け口」はその1つに分類されます。別名「下顎前突(かがくぜんとつ)」とも言います。
「受け口」の主な原因としては、「遺伝」や「小さい頃のお口周りの癖」、「口呼吸」が挙げられます。
受け口の2つのケース「歯の生え方」と「骨格」について
受け口治療では、「2つのケースにおける見極め」が重要です。そのケースの違いには、「歯の生え方」「骨格の問題」があり、それぞれ治療方法や治療の難易度が異なります。これらの違いについてご説明します。
① 歯の生え方に原因があるケース
歯の生え方によって受け口になっている状態です。上の前歯が下の前歯より内側の位置に生えていたり、傾いて生えていたり、下の前歯が上の前歯より外側の位置に生えている、あるいは傾いて生えている状態をいいます。このような状態だと、正常な咬み合わせとは反対になり、受け口になります。「骨格性」との大きな違いは、顎骨に問題はなく歯の生え方に問題があるということです。
➁顎の骨格に原因があるケース
歯が生える土台となる顎骨が原因で受け口になっている状態です。上顎より下顎の成長が著しく大きくなった状態や、上顎の成長不足により下顎の方が大きくなった状態になると受け口になります。
また、下顎が上顎より前方にズレている状態も受け口になります。
このような状態だと、咬み合わせの基礎となる顎骨が原因となっているため、治療の難易度が高くなります。
同じ受け口でも、原因によって歯列矯正の難易度が異なります。早い時期に治療を始める方が受け口が治りやすいこともあるので、受け口に気づいたら早めに歯科医院で相談してみましょう。
似ているようで違う!?「受け口」と「しゃくれ」
「受け口」と「しゃくれ」は似ていますが、大きな違いがあります。この違いにより、治療方法も異なるため、治療を行う際はこれらの違いを見極めることが重要になります。
▷受け口
上下の咬み合わせが反対になっている状態のことを言います。つまり、下の前歯が上の前歯より外側に出ている状態が「受け口」です。
下顎が前に出ていることで、しゃくれているように見えることもありますが、「受け口」は歯並びや咬み合わせが原因で起こります。
▷しゃくれ
横顔を見たときに、下顎の先が前方に出ている状態のことを言います。特に咬み合わせや歯並びに問題がなくても、「しゃくれ」の状態になっていることもあります。
「しゃくれ」の原因は下顎の大きさや形です。上顎が正常に成長していない場合や、下顎が縦向きに長い場合に、下顎が前に出ているような印象になりやすいです。
受け口を引き起こす要因「先天的要因」と「後天的要因」
受け口を改善するには、まずその原因を知ることが重要です。受け口の原因には、大きく分けて2つ「先天的要因」と「後天的要因」があります。それぞれ、詳しく解説します。
Ⅰ.先天的要因
「先天的」とは生まれつき備わっている性質を意味します。先天的要因では、遺伝的な要因が大きく関係します。両親や祖父母に受け口の人がいる場合は、受け口が子供や孫に遺伝する確率が高いです。受け口自体がそのまま遺伝するわけではなく、「歯の生え方」「歯の数や大きさ」「顎骨の大きさ」などが遺伝することによって、受け口になりやすくなります。
特に、通常の歯より小さい「矮小歯(わいしょうし)」や、もともと歯が欠損している「先天欠如歯(せんてんけつじょし)」があると、上下で歯の本数が異なったり、咬み合う位置が正常な位置よりズレたりすることで、受け口になる可能性があります。
Ⅱ.後天的要因
「後天的」とは、生まれたあとで備わった性質を意味します。「舌の位置」や小さい頃からの「口周りの癖」「間違った呼吸方法」などが原因です。
舌の位置が間違った位置にあると、受け口になりやすくなります。舌の位置は、スポットと呼ばれる上前歯根元付近の歯茎に舌の先端が触れて、舌全体は上顎に吸着している状態が正常です。しかし、舌の位置が下がり、下の歯列の内側に舌が置かれた状態になると、舌により下の歯が外側に押されることによって受け口になることがあります。また、舌を口の外に出す癖があると、受け口を引き起こしやすくなります。
他にも、上唇を前歯で噛む癖があると、上唇が内側に入る力により、上前歯が内側に押されることで、下前歯が外側に出やすくなり、受け口になりやすくなります。
口呼吸が習慣になっていると、常時口が開かれた状態になるため、舌の位置が下がりやすく、受け口を引き起こす原因になります。
「受け口」の症状に合った治療法とは?症状別に解説!
受け口の原因や治療を始めるタイミングの違いによって、治療法が変わります。
①歯の生え方に原因がある場合の治療法
歯列矯正での治療が可能です。歯列矯正には、主に2つワイヤー矯正とマウスピース矯正があります。
ワイヤー矯正では、歯の表面に装置(ブラケット)を接着し、そこにワイヤーを通すことで歯を動かします。歯の表側に装置をつける方法を表側矯正、裏側につける方法を裏側矯正と言います。表側矯正は装置が目立ちやすいですが、裏側矯正は装置が目立ちにくいです。注意点は、装置の取り外しが自分でできないことです。食事や歯磨きがしづらく、うまくケアできていないと虫歯や歯周病リスクが高まります。
大きな特徴は、歯を大きく動かすことが可能なため、歯の移動距離が多くなるような難易度の高い症例でも適応できます。
マウスピース矯正は、透明なマウスピース型の矯正装置を使用するため目立ちにくく、取り外しも可能なため通常通り食事や歯磨きが行えます。自分で装置の交換が可能なため通院回数も比較的少ないです。ただし、装置の装着時間(1日20時間以上)、交換時期(基本的には2週間毎)を自分で管理する必要があります。
歯列矯正期間は基本的に2~3年、重度の場合は5年くらいかかることもあります。費用は、ワイヤー矯正であれば、表側矯正は60~80万、裏側矯正は80~150万、マウスピース矯正なら80~100万円くらいが目安です。裏側矯正は、歯列矯正の中でも高度の技術が必要になるため高額になりやすいです。
②顎の骨格に原因がある場合の治療法
骨格に問題がある場合は、歯列矯正と併せて外科治療が必要になります。歯科医師から顎変形症と診断を受けた際には、厚生労働省の定めにより保険適用で歯列矯正と外科手術を受けることができます。その場合は、認定を受けた医療機関で治療を受けることになります。
顎変形症の場合、顎の成長が止まってから治療を行うので、治療時期は16~17歳以降が目安です。
費用に関しては、保険適用で外科治療と歯列矯正を受けた場合、合計でおおよそ60~80万円です。
骨格に問題がある受け口は、歯列矯正と外科治療を併用することで、骨格のズレや咬み合わせ、歯並び、顔面の歪みを根本的に解決することが可能になります。
治療期間の目安は3年くらいです。
(基本的な治療の流れ)
1.外科手術前の歯列矯正(約6ヶ月~2年)
2.外科手術(手術前日~術後約10日間の入院)
3.外科手術後の歯列矯正(約1年)
4.リテーナー装置を使用し保定(後戻りを防ぐため)
③子供の時期に始める場合の治療法
4歳~10歳頃の子供の時期に行う歯列矯正を、予防矯正あるいは小児矯正といいます。
顎の骨格に原因がある受け口は、早期の治療で効果が出やすいです。年齢は早くて4歳から始めることができ、5歳前後で始めることが理想的です。この時期は、顎の発達時期と永久歯への生え換わりの時期であるため、歯列矯正を行うことにより顎の発達や歯の生え換わりを正常に促すことができます。
早期に歯列矯正を始めるとメリットが多いです。
(小児矯正のメリット)
・将来的に歯列矯正による便宜抜歯の可能性が低い
・大人と比較して骨が軟らかいため歯が動きやすい
・マウスピース型の装置を使用するため治療の負担が少ない
装置は、シリコン素材の柔らかめのマウスピースを使用します。歯を移動させるというよりは、小さいうちから舌の位置を正常な位置に導くことや、お口全体の筋肉を鍛えることを目的としています。それに伴って、歯が正常な位置に生えることで歯並びや咬み合わせも改善しやすくなります。
マウスピースの装置は日中1時間、就寝時に装着し、10分ほどのお口のトレーニングを毎日行います。(体調不良などでできない場合はお休みすることも可能です。)
他にも、顎の内側に固定して装着する「急速拡大装置」により顎骨の成長を促しながら顎骨を横方向に拡大する方法もあります。このような方式で取り外しできる装置「床矯正」を使用する場合もあります。
小児矯正の費用は、精密検査、定期的な診察、お口のトレーニング、装置代など全て含めて60~80万円くらいが目安となります。期間はおおよそ2~3年くらいですが、生え換わりの状態によって変動します。
受け口治療で外科手術が必要になるケースとは?
受け口で顎の骨格に問題がある場合は、歯列矯正のみでは改善が難しく、顎骨に対して外科手術が必要です。
骨格に問題があるケースとしては、「下顎が上顎より外側に出ている」「下顎の骨が上顎に比べて大きい」「上顎の骨が下顎より小さい」ことなどが挙げられます。
このケースでは、「セットバック法」という外科手術が適応されることが多いです。
治療法を簡単に説明すると、最初に下顎の歯を左右1本ずつ抜歯します。基本的には下顎の第一小臼歯あるいは第二小臼歯を抜歯するケースが多いです。
次に、顎骨を切り離して抜歯したスペースを利用し、後方に移動させ固定します。固定するときは骨自体はチタンプレート、歯はワイヤーを使用します。歯に取り付けたワイヤーは約3ヶ月で取り外し、歯列矯正をスタートさせます。骨につけたチタンプレートは、半年~1年程度で取り外します。
手術を行う部位は、口の内側から行うので、傷口はほとんどわからず目立つことはありません。外科手術を併用した歯列矯正は、入院も必要となり大がかりな治療になりますが、顎骨自体の形態を変えること、それに併せて歯並びを整えることで、咬み合わせを根本的に改善することができます。
受け口は自分で改善できる?
受け口は自然に改善することはないのか、できれば自分でなんとかしたい、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
2歳頃までのお子さんであれば、約50%の確率で受け口が治ることもあると言われています。乳歯が生え揃う頃である3歳をすぎると、自然と治る確率はさらに低くなります。
骨格に問題がみられない軽度の受け口であれば、お口のトレーニングや咬み合わせを意識することによって改善できる場合もあります。その際には、唇や舌などの口周りの筋肉を鍛えるために、舌を正しい位置に置くトレーニングや、唇を閉じるトレーニングなどを行います。
ただし、自力でトレーニングを進める場合、どれくらいの時間がかかるのか、どのくらい改善しているのか、見通しが立ちにくく無駄に時間がかかってしまいます。
また、自己判断で行うことにより、知らず知らずのうちにお口の状態に適さないトレーニングを継続してしまうことで、歯並びが悪化することもあります。歯並びや咬み合わせは、一度ズレを生じると治すのに費用がかかったり、期間がかかります。
そのため、歯並びや咬み合わせを改善するには、専門的な知識が必要です。まずは、歯科医院に相談することをおすすめします。
受け口を解消しやすくなる3つのトレーニング
「受け口」の症状を緩和するトレーニング方法です。このトレーニングを行えば、必ず「受け口」が改善するというものではありませんが、「受け口」の悪化予防にもなるので、ぜひ試してみてください。
◇舌ポジションを覚えるトレーニング
舌の正しい位置を身につけるためのトレーニングです。
舌の正しい位置は、舌の先端が上前歯裏側の根元付近の歯茎(スポット)に触れ、舌全体が上顎に吸着している状態です。この状態で舌を5秒間保ちます。
これを毎日5~10回繰り返し行い、舌を正しい位置に置けるように習慣化します。
◇舌回しトレーニング
舌を回すことで、舌の筋肉を鍛えます。口周りの筋肉や舌が鍛えられることで、就寝時のイビキやほうれい線などのシワの予防にも繋がります。
(やり方)
1.口を閉じます。
2.舌を右下奥歯のほっぺた側に置きます。
3.そのまま、舌を左奥歯まで動かします。
(下の前歯が出ている部分は舌で少し押すような感覚で動かしてみましょう)
4.同じように左下奥歯から右下奥歯へ舌を動かします。
5.次は、舌を歯の内側に移動させます。
6.舌を右上奥歯から左上奥歯へ移動させます。
7.そのまま、舌を左上奥歯から右上奥歯まで動かします。
1~7の順序で、1セット10回を3セット繰り返しましょう。仕事や勉強の休憩時間などにもできるので、タイミングを見つけて行ってみましょう。
◇パタカラ体操
この体操は、舌や唇などの口周りの筋肉から喉の筋肉を鍛えることができます。そのため、食事の際の飲み込みをスムーズにする効果も期待できます。
(やり方)
1.上下の唇を合わせて「パッ」と音を出します。
2.上顎に舌をあてて「タッ」と音が出るように下顎まで下ろします。
3.口を開けた状態で、喉を一時的に閉じて「カッ」と音を出します。
4.舌を丸めながら「ラ」と音を出します。
「パ」「タ」「カ」「ラ」と一文字ずつ発音する方法、「パパパ…」「タタタ…」「カカカ…」「ラララ…」と連続的に発音する方法、全ての音が入っている文「パンダのたからもの」と発音する方法などがあるので、自分に合った方法で行ってみましょう。1日10回程度行うと効果的です。
当院は受け口治療も行っております!お気軽にご相談を!
受け口の治療は、歯列矯正の中では難易度の高い治療です。しかし、軽度から重度まで様々な状態があり、診断によってはマウスピース矯正で改善が可能な症例もあります。ただし、骨格が原因となっていて外科治療が必要な症例では、マウスピース矯正が適応できず、ワイヤー矯正で治療を行うことがほとんどです。
受け口で悩まれている方は、まず最初に歯科医院でお口の状態を診てもらうことをおすすめします。当院では、無料カウンセリングも受付けております。
「自分の受け口の原因を知りたい」「難易度の高い症例なのかどうか」「治療後のお口の状態をシミュレーションしたい」など、歯列矯正についての疑問やお悩み、どんなことでも構いません。お気軽にお問い合わせください。