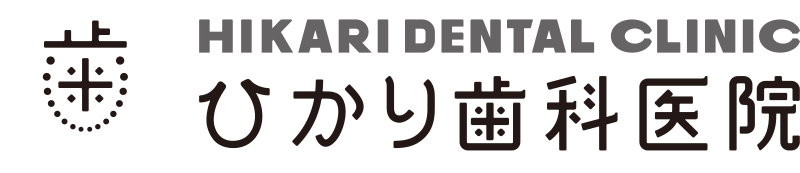治療は必要?正しい咬み合わせの基準と治療方法について
【監修:歯科医師 長谷川雄士】

歯がキレイに並んでいても、咬み合わせが良くないこともあります。見た目が整っているかという審美面に目が行きがちですが、歯は、正しく咬み合っていないと本来の役割を果たすことができません。
そこで知っていただきたいのが、正しい咬み合わせの基準です。
このコラムでは、ご自宅で簡単に咬み合わせをチェックできる項目と、咬み合わせ治療について解説しております。
歯並びや咬み合わせについて気になることがある方は、ぜひご参考になさってみてください。
【目次】
1.矯正医が基準とする「正しい咬み合わせ」について
2.整った咬み合わせがもたらす体へのメリット
2-1歯並び・咬み合わせが悪い「不正咬合」の症例
3.咬み合わせ治療は主に3つ!治療別に解説します
3-1咬合調整
3-2補綴治療
3-3矯正治療
4.歯並び・咬み合わせが気になる方は、ぜひ当院へ!
矯正医が基準とする「正しい咬み合わせ」について
矯正治療においてゴールとする「正しい咬み合わせ」は様々あり、分かりやすい主な項目を挙げて解説します。
- 顎の骨格や咬み合わせに違和感や痛みがない
- 左右両方の臼歯がバランスよく咬み合っている
- 数回カチカチと歯を咬み合わせたときに、下の前歯が上の前歯に過度にあたらない
- 上下の犬歯が咬み合っている
- 左右にギリギリ咬み合わせをずらした時に、上下の犬歯が接触する
- 左右にギリギリ咬み合わせをずらした時に、上下の臼歯が接触しない
- 下の犬歯が、上の前歯2番目の歯(側切歯)と犬歯の間で咬み合っている
- 歯を咬み合わせたときに、上下間で目立った隙間がない
上記の項目の中に気になることがあれば、一度、歯科医院に相談しましょう。
整った咬み合わせがもたらす体へのメリット
◇口元がキレイ
歯並びがデコボコしている「叢生:そうせい」、上下の前歯の間に隙間がある「開咬」、前歯が前方に突出する「出っ歯」など、コンプレックスを感じてしまう方もいらっしゃいます。歯並びや咬み合わせを整えることは、自分の表情や笑顔に自信を持つことができ、人との会話や食事を楽しむこともできます。
◇歯の寿命がのびる
上下の歯がバランスよく咬み合うと、歯に大きな負担がかかりにくいです。咬み合わせが悪いと、咬む力が偏ってしまい、歯が欠けたり割れたりすることもあります。自分の歯を長く使い続けるためにも、咬み合わせは重要です。
◇虫歯や歯周病になりにくい
歯並びや咬み合わせが整っていると、歯磨きがしやすいため、虫歯や歯周病の予防に繋がります。
また、不正咬合に分類される「出っ歯」や「開咬」、「受け口」の状態だと、口呼吸になりやすいです。口呼吸は口が乾燥しやすく唾液の循環が悪くなるため、虫歯や歯周病のリスクが高まります。
◇顎関節への負担がかかりにくい
咬み合わせのバランスが悪いと、咬んだときの力が左右片方に強くかかったり、上下の顎がずれた状態で食べ物を咀嚼したりしていることがあります。そうすると、歯への負担だけではなく、顎関節にも大きな負担がかかり、顎関節症のリスクを高めてしまいます。左右均等に咬めると、顎関節への負担を軽減することができます。
◇しっかりと咀嚼できる
咬み合わせが良いと、全ての歯がバランス良く咬み合うので、しっかりと咀嚼でき、食物が十分にすり潰された状態で飲み込むことができます。そうすると、お口周りの筋肉が鍛えられるのはもちろん、胃や腸などの消化器官への負担が減り、栄養の吸収も良くなります。咬み合わせのバランスが良いと、全身にも良い影響があります。
◇肩こり・頭痛になりにくい
咬み合わせのバランスが悪いと、咬む力が偏ります。その偏りにより、筋肉に過剰な力がかかり、筋肉が緊張します。顎の筋肉は頭や首の骨、筋肉に繋がっているため、筋肉の緊張により、頭痛や肩こりなどを引き起こしやすいです。咬み合わせのバランスを整えることで、筋肉への過度な負担を防ぐことができます。
歯並び・咬み合わせが悪い「不正咬合」の症例
歯並びや咬み合わせが悪い状態を「不正咬合(ふせいこうごう)」と言います。不正咬合の代表的な例に「叢生(そうせい)」「出っ歯」「受け口」「過蓋咬合」が挙げられます。これらの特徴について、項目別に説明します。
▶叢生
顎の大きさに対して歯が大きいと、歯が生えるスペースが確保されにくくなります。そうすると、歯は本来生える位置の前後にずれて生えてくることもあり、歯並びがデコボコします。これを叢生と言います。
叢生になると、歯と歯がうまく咬み合わないだけでなく、歯と歯が重なることで歯磨きがしにくい状態になり、虫歯や歯周病などのリスクを高めてしまいます。
▶出っ歯
上の前歯が前方に突出している状態です。上顎の過成長や、前歯が前方に傾いて生えることで引き起こされます。前歯がうまく噛み合わないため奥歯の負担が大きく、また、前歯が突出していて唇が閉じにくいため口が乾燥しやすくなります。お口が乾燥すると、唾液の循環が悪くなることで、虫歯や歯周病のリスクを高めてしまいます。
▶受け口
下の前歯が上の前歯より外側に出ている状態です。下顎が上顎より大きく成長していたり、下の前歯が外側に傾いて生えた場合に引き起こされます。
正常な咬み合わせに比べて舌の位置が下がりやすいため(低位舌)、口呼吸になりやすいです。口呼吸は、お口の乾燥や免疫力の低下などの原因にもなることもあります。
▶過蓋咬合
下の前歯がほとんど見えなくなるくらい、上の前歯が被さっている状態です。歯並び自体は綺麗なこともあるため気づかれにくいですが、上下の前歯の咬み込みが強く、歯や歯茎にダメージが加わりやすいです。下の前歯が上の前歯の歯茎にあたっている場合は、歯茎が傷つき痛みが生じることがあります。また、食いしばりの癖がある方は、症状が悪化することもあります。
咬み合わせ治療は主に3つ!治療別に解説します
咬み合わせの治療には、「咬合調整」「補綴治療」「矯正治療」があります。それぞれの治療方法について具体的に解説します。
咬合調整
咬む力が一部の歯に集中しないように、咬み合わせのバランスを整えます。歯だけではなく歯周組織にもダメージを与えてしまう「咬合性外傷」や、下顎を左右にずらすと違和感がある場合に適用されることが多いです。
治療方法としては、青色と赤色の咬合紙をそれぞれ患者さんに咬んでもらいます。赤色の咬合紙を噛むときはカチカチ、青色の咬合紙を噛むときはギリギリと横に動かします。そうすると、赤と青の印が歯につきます。この印がついた部分を基準にして、歯を少しずつ削りながら咬み合わせを調整します。削る部分はエナメル質の範囲内であるため、歯に大きなダメージを与えることはありません。
調整後、1週間後くらいに来院していただき、日常生活で違和感があるようなら、再調整を行います。半年~1年くらいは、定期的に経過観察を行います。
[注意事項]
咬み合う位置が低くならないように削りすぎないことや、横向きにずらしたときにかかる力を抑えられるように調整することが重要です。
[費用目安]
保険診療が適用されれば3000円前後ですが、自由診療となる場合もあります。
補綴治療
補綴治療とは、虫歯などが原因で歯の一部を失った場合に、詰め物や被せ物で歯を補強する治療のことです。何らかの原因で(虫歯、歯周病、事故など)歯自体を失った場合に、人工歯で補う治療「ブリッジ」「入れ歯」「インプラント」も補綴治療に含まれます。
ブリッジ
欠損した部分に隣接する両側の歯を支えとして欠損部に歯を作る治療方法です。被せ物がつけられるように、両側の歯を削って形を整えます。欠損部分は人工歯(ポンティック)で補い、両側の被せ物と繋げます。これを装着することで、元の歯のように使うことができます。比較的、違和感が出にくいです。
治療は、早くて1ヶ月くらいで終了しますが、咬み合わせが複雑な場合や神経の治療が必要な場合は、2〜3ヶ月かかることもあります。
[注意事項]
歯を1本失っている分、両側の歯に噛む力がかかりやすいため、正しいケアが大切です。
人工歯の下部に食べ物が詰まることがあります。
[費用目安]
保険診療が適用される場合、前歯なら2万円程度、奥歯なら1万円程度です。セラミックなど保険適用外の素材を選ぶ場合は、1本10万円前後のため、被せ物3歯分で30万円前後の費用がかかります。
入れ歯
欠損した部分に隣接する歯に金具やフックをかけて、欠損部分の人工歯を支える治療方法です。取り外し可能で、ブリッジのように他の歯を削ることはありません。
保険診療では、部分入れ歯なら2週間~1ヶ月程で作製でき、総入れ歯は1ヶ月程かかります。入れ歯が接触する部分の歯茎の状態は変化しやすいため、その状態に合わせて入れ歯のフィット感や咬み合わせを調整しながら、なるべく違和感がないようにします。
材質や見た目にこだわるのであれば、保険外診療で入れ歯を作製することも可能です。その場合の入れ歯作製期間は、2~3ヶ月程かかります。
[注意事項]
入れ歯を支える金具が口元から見えて金属色が気になったり、取り外した時にそのまま置き忘れたりする可能性があります。
[費用目安]
保険診療の入れ歯の場合、5000~1万5千円くらいの金額です。
保険外診療の、軽くて薄い「金属床」は約50~80万円、インプラントで固定する「インプラントデンチャー」は約50~200万円、マグネットで固定する「マグネットデンチャー」は約3000円~10万円です。
(部分入れ歯か総入れ歯かでも金額が異なります)
インプラント
歯が欠損した部分の顎骨に人工歯根を埋め込みます。人工歯根の素材に使用されているチタンは生体親和性が高いです。また、隣の歯を削ったり、支えにするために引っかけたりしないので、他の歯に負担がかかりにくく、元の歯と同じように噛むことができます。
治療期間は約1年です。治療の間は仮歯を使用して、なるべく生活に支障が出ないようにします。
[注意事項]
外科手術が必要となります。保険外診療となるため費用が高額になりやすいです。
[費用目安]
1本40万~60万円です。歯周病などで骨量が減少している場合は、骨を追加する治療が必要で、追加費用がかかります。
矯正治療
ワイヤーやマウスピースなどの装置を使用して歯自体を移動させ、歯並びや咬み合わせを整えます。そのため、歯並びや咬み合わせの根本的な改善が期待できます。
ワイヤー矯正
歯の面に装置(ブラケット)を装着し、そこにワイヤーを通して歯を3次元的に動かします。歯の表面に装置を接着する「表側矯正」と、裏側に接着する「裏側矯正」があります。歯を大きく移動できるため、適応症例範囲が広いです。
治療期間は、全体矯正であれば2~3年、部分矯正であれば半年~1年くらいです。通院頻度は、歯並びの状態によって個人差がありますが、月1回くらいになります。
[注意事項]
装置が歯に接着しているため、歯磨きがしづらく虫歯や歯周病のリスクが高まりやすいです。
比較的歯を大きく動かすため痛みを感じやすい傾向があります。
保険外診療のため費用が高額です。
[費用目安]
全体矯正の場合、表側矯正だと60~100万円くらい、裏側矯正だと110~150万円くらいです。(裏側矯正は高度な技術が必要なため、表側矯正よりも費用がかかります)
装置の素材は金属が一般的ですが、オプションで白や透明のプラスチック素材に変えることができます。ワイヤーも白色に変更可能です。
マウスピース矯正
歯科医院で歯並びに合わせたマウスピースを作製し、そのマウスピースを決まった日数毎に自宅で交換します。少しずつ歯を動かすので比較的痛みを感じにくく、装置が透明であるため目立ちにくいです。また、取り外しもできるため、食事や歯磨きが普段通りに行えます。
治療期間は、全体矯正であれば2~3年、部分矯正であれば半年~1年くらいです。通院頻度は、歯並びの状態によって個人差がありますが、2ヶ月に1回くらいになります。
[注意事項]
マウスピースの交換時期(基本的には2週間毎)や装置の装着時間(1日20時間以上)を守らないと、治療期間が延びたり、装置の再作成が必要になったりすることがあります。そのため、自己管理がとても大切です。
また、保険外診療のため費用が高額です。
[費用目安]
全体矯正で80~120万円くらいです。
歯並び・咬み合わせが気になる方は、ぜひ当院へ!
歯並びや咬み合わせは、見た目はもちろんのこと、体の機能にも影響します。咬み合わせが整っていると、食べ物をしっかりと咀嚼できるため、消化や栄養の吸収が良くなります。話をするときも発音や滑舌が良くなりやすいです。また、口元から見える歯並びは、第一印象にも良い影響を与え、対人関係の自信にも繋がるでしょう。
当院でも、咬み合わせ治療を行っております。歯は、髪の毛を1本咬んだだけでも違和感があるくらい繊細です。そのため、まずは精密検査を行います。虫歯や歯周病のチェック、レントゲン、お口や顔の歪みを確認する写真撮影、スキャナーによるお口の型採りなどを行って、歯並びや咬み合わせの状態を診断します。その資料を使って、治療の効果やリスクを含めて治療計画を説明させていただきます。患者様に納得していただいた上で治療を開始いたしますので、疑問や不安など、気になることがあればご相談ください。
当院では、無料カウンセリングも実施しています。お気軽にお問い合わせください。