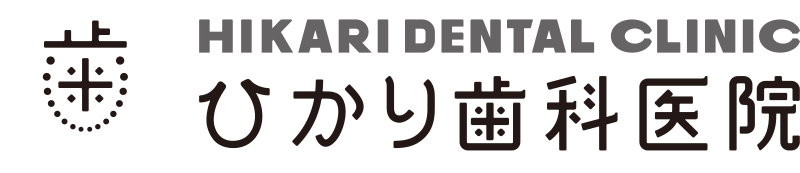歯周病の進行メカニズムとは?治療法と予防法も解説
【監修:歯科医師 長谷川雄士】

歯周病は、進行するとお口の中だけではなく全身へ影響を及ぼすことがある病気です。また、歯周病が重症化してしまうと、歯が抜けてしまう可能性もあります。厚生労働省の報告においては、日本での歯周病患者割合は47.9%と高いです。
「歯周病」という言葉は聞いたことあるけど、その原因や予防法がよくわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は、歯周病の「原因」、「進行段階」、「予防法」などについてわかりやすくお伝えします。
【目次】
1.歯周病の主な原因について
2.歯周病はどのように進行する?進行メカニズムについて
2-1[ステージ1]
2-2[ステージ2]
2-3[ステージ3]
2-4[ステージ4]
3.歯周病を予防するためにできること
3-1 ①正しい歯磨きを身につける
3-2 ➁定期検診・クリーニングを受ける
3-3 ③生活習慣を見直しコントロールする
3-4 ④歯列矯正で歯並び・咬み合せを整える
4.ケアしやすいインビザラインで歯周病リスクを下げる!
歯周病の主な原因について
歯周病は、歯と歯茎の間に付着したプラークが主な原因となって引き起こされるお口の病気です。
プラーク1mg中には、1億~2億もの細菌が存在します。プラークが蓄積すると、その細菌が歯と歯茎の溝に入り込むことで細菌感染を引き起こし、歯茎に炎症が生じます。それによって、歯と歯茎の溝部分に歯周ポケットが形成され、溝がさらに深くなります。
歯周ポケットが深くなるほど、細菌が停滞し内部にも侵入しやすく、歯を支えている骨(歯槽骨)に細菌が到達することで、歯槽骨が吸収されていきます。その結果、支えを失った歯はグラついて抜けてしまうことがあるのです。
歯周病は「サイレントディジーズ(静かに進行する病気)」とも呼ばれ、大きな症状がほとんどない状態で進んでいきます。そのため、気づいたときには歯周病が重症化しているケースもあります。
したがって、歯周病の進行を防いだり予防を行なうには、早めに気づくことが非常に大切になります。
歯周病はどのように進行する?進行メカニズムについて
歯周病には進行段階があります。
【ステージ①】歯肉炎→【ステージ②】軽度歯周炎→【ステージ③】中等度歯周炎→【ステージ④】重度歯周炎
ステージ①の状態では、ほとんど症状を感じることはありません。歯科医院を受診した際に発見され、気づくこともあります。
ステージ②の状態から、歯茎の腫脹や出血、痛みやイジイジする違和感などの症状が出始めます。
ステージ③からは、ステージ②のような症状に加え、歯のグラつきも感じるようになり、食事に支障が出るケースもあります。
ステージ④になると、歯を残すことさえも難しい状態になり、場合によっては抜歯が必要です。
歯周病はゆっくり時間をかけて進んでいき、大きな症状がでにくいです。歯茎の違和感や、鏡でお口の中を見た際に歯茎が赤みを帯びている、などの症状があるようなら、一度、歯科医院を受診してみましょう。
以下に、歯周病の診断基準と、ステージごとの症状について詳しく解説します。
[ステージ1]
歯肉炎
| 症状 | ・自覚症状はほとんど感じられません。 ・歯茎が赤みを帯びたり、歯磨き中に出血が見られることがあります。 ・歯を支えている骨(歯槽骨)にはほとんど影響がありません。 |
| 歯周ポケットの深さ | 4mm以内 |
| セルフケアと治療法 | ・歯と歯茎の間を、システマタイプの軟らかい歯ブラシで磨くと効果的です。
・正しく歯磨きを行なえば、元の健康な歯茎の状態に改善できます。
・歯科医院では、歯周ポケット内を専用の器械で洗浄し、歯の表面に付着している歯石を除去することで歯茎を改善します。 |
[ステージ2]
軽度歯周炎
| 症状 | ・「歯肉炎」と同じように、歯茎に赤みを帯び、出血が見られます。
・「歯肉炎」との大きな違いは、「歯槽骨の吸収」です。
・歯槽骨の吸収が起こると、歯を支える骨が減少することで歯周ポケットが形成され、歯周病が進行しやすくなります。 |
| 歯周ポケットの深さ | 5mm以内 |
| セルフケアと治療法 | ・歯周ポケットが深くなっているため、歯茎で隠れている歯の根元まで歯石がついていることがあります。
・歯科医院で専用の器械を用いて歯周ポケット内部を洗浄し、歯石を除去します。
・セルフケアでは、歯と歯の間、歯と歯茎の間など細かい部分まで歯ブラシを当てるようにして、プラークの蓄積を防ぎましょう。
・出血があっても、できるだけ優しく歯ブラシをあてるようにすると、歯茎が改善しやすいです。 |
[ステージ3]
中等度歯周炎
| 症状 | ・歯茎が赤みを帯びて炎症が強くなり、歯茎からの出血がみられます。
・歯槽骨の吸収が進み、歯を支えている骨が減少することで、歯が支えきれずグラつきを感じることがあります。
・歯と歯を咬み合わせた時の刺激で痛みを感じることがあり、食事の際に支障をきたすこともあります。また、歯茎から白色~黄白色をした膿が出てきたり、口臭の悪化を感じたりすることもあります。 |
| 歯周ポケットの深さ | 6mm以上 |
| セルフケアと治療法 | ・歯科医院で、深くなっている歯周ポケット内部を専用の器械で洗浄します。
・歯周ポケット内部に付着した歯石は硬くなっています。一度に除去できないようなら、数回に分けて歯石除去を行います。状態によっては痛みが伴うため、麻酔が必要な場合もあります。
・セルフケアでは、歯茎が下がって隙間があいている場合は、歯ブラシだけではなく歯間ブラシを使用していただくと効果的です。 |
[ステージ4]
重度歯周炎
| 症状 | ・歯茎が赤~赤紫色を帯び、炎症が非常に強く、歯茎がブヨブヨしています。 ・食事の際に出血したり、歯磨きの際に膿がでたりすることがあります。 ・歯槽骨が正常な状態より半分以上失われることで、歯のグラつきが強まり、食事の際に痛みが生じることもあります。 ・口臭が悪化します。 |
| 歯周ポケットの深さ | 7mm以上 |
| セルフケアと治療法 | ・歯茎の改善が難しい状態です。
・症状の進行を防ぐために、歯周ポケットの洗浄や歯石除去を行います。
・症状が落ち着かない場合は、抜歯を行うことがあります。
・歯を残せる場合のセルフケアとしては、プラークの付着をなるべく防げるように、歯ブラシと一緒にタフトブラシや歯間ブラシを使用して丁寧に歯磨きをしましょう。 |
歯周病を予防するためにできること
歯周病を予防する方法には、「毎日の歯磨き」、「定期的なクリーニング」、「生活習慣の見直し」、「歯列矯正」があります。
項目毎に解説します。
①正しい歯磨きを身につける
歯周病の主な原因は歯に付着したプラークであるため、歯周病予防には毎日の歯磨きが欠かせません。
プラークが付着しやすい部分は、歯と歯が咬み合う溝、歯と歯の間、歯と歯茎の間です。これらの部分を意識しながら磨きましょう。
歯ブラシは大きく動かすと汚れが除去しにくいので、歯2本分くらいの幅で小刻みにシャカシャカ音がするように磨きます。歯茎に痛みがある場合は、毛先が細くて軟らかい歯ブラシの使用をおすすめいたします。
また、清掃補助用具を歯ブラシと一緒に使用していただくことも、プラーク除去に効果的です。
歯と歯の間はデンタルフロス、歯と歯の間に隙間がある場合は歯間ブラシ、歯と歯が重なっている部分にはタフトブラシを使用してプラークの蓄積を防ぎましょう。
➁定期検診・クリーニングを受ける
歯科医院での定期的なクリーニングも歯周病予防に効果的です。歯ブラシが届かない、深くなった歯周ポケット内部の洗浄や、歯石除去、歯磨き指導などを受けることができます。それによって、お口の中の細菌を激減させるとともに、正しい歯磨きを身につけることができます。
歯周病は再発しやすい病気です。一度治療を行なったら終わりではなく、治療後にも定期的なクリーニングを受けて再発を防ぐようにしましょう。
<定期検診・クリーニングの内容>
1、歯周病検査
・レントゲン撮影
・歯周ポケットの深さの測定
・歯のぐらつきの確認(歯の動揺度をⅠ〜Ⅲ段階で検査)
2、歯磨きのやり方の確認・指導
3、お口の中や咬み合わせの確認
4、随時問診を行う(生活習慣や服用薬などを確認)
5、歯のクリーニング(歯周ポケット内の洗浄・歯石除去)
③生活習慣を見直しコントロールする
歯周病の「リスクファクター」となるのは、「喫煙」と「糖尿病」です。つまり、喫煙や糖尿病により、歯周病になりやすくなる、あるいは進行しやすくなるということです。
<喫煙がもたらすリスク>
タバコに含まれるニコチンという成分によって、血管が細くなり血の流れが悪くなります。そのため、歯周病が進行していても歯茎の腫れや出血などの症状が出にくく、より歯周病に気づきにくい傾向があります。
また、歯周病治療を行なっても歯茎が改善しにくいとも言われています。
<糖尿病がもたらすリスク>
糖尿病は、血液中のブドウ糖(血糖)の濃度が高まってしまう病気です。糖がうまく代謝されず、血管内部に糖の代謝産物が付着します。それによって血管が弱り、体の新陳代謝も低下するため傷口や炎症の治りが悪くなり、歯周病の発症や進行が早まるリスクが高まります。
「喫煙」や「糖尿病」は、体の抵抗力を弱めてしまうため、歯周組織が破壊されやすくなります。
しかし、「喫煙」においてタバコの本数を減らしたり、「糖尿病」においては食事内容を見直すなど、生活習慣を少しずつコントロールすることでこれらのリスクを下げることができます。
④歯列矯正で歯並び・咬み合せを整える
歯並びや咬み合せを改善することで、歯周病リスクを下げられる可能性があります。
歯が重なっていたり傾いていたりすると歯ブラシがうまくあたらず、プラークが残りやすいです。
また、歯並びだけではなく咬み合せのバランスも悪いと、咬む力が部分的に集中して歯や歯周組織に過度な負荷がかかるため、歯周病が進行しやすくなることもあります。
矯正治療で歯並びや咬み合せを整えることによって、お口の中のケアがしやすくなり、バランス良く歯を咬み合わせることができます。見た目や機能面の改善以外にも、歯周病や虫歯を予防する効果も得られるのです。
ケアしやすいインビザラインで歯周病リスクを下げる!
矯正治療と聞くと、治療期間が長く、何度も歯科医院に通院するイメージがありませんか?そんな方におすすめなのが「インビザライン」です。
「インビザライン」はマウスピース矯正の1つで、透明なマウスピース型の矯正装置を定期的に交換しながら、歯を動かして歯並びを整えます。ご自宅でマウスピースの交換ができるため、通院頻度は比較的少なく、効率的に歯を動かすことができます。
また、従来のワイヤー矯正は装置の着脱ができないため、お口のケアが難しく、虫歯や歯周病のリスクが懸念されていました。しかし、インビザラインは装置を取り外せるため、通常通り歯磨きを行うことができます。食事も通常通りでき、見た目も目立ちにくいため、日常生活でのストレスが少ないのも大きな特徴です。
インビザラインでの矯正治療では、「治療中のケアのしやすさ」「歯並びが整う」「見た目はもちろん咬み合わせの改善」などにより歯周病リスクの改善が期待できます。気になることがある方は、お気軽にご相談ください。